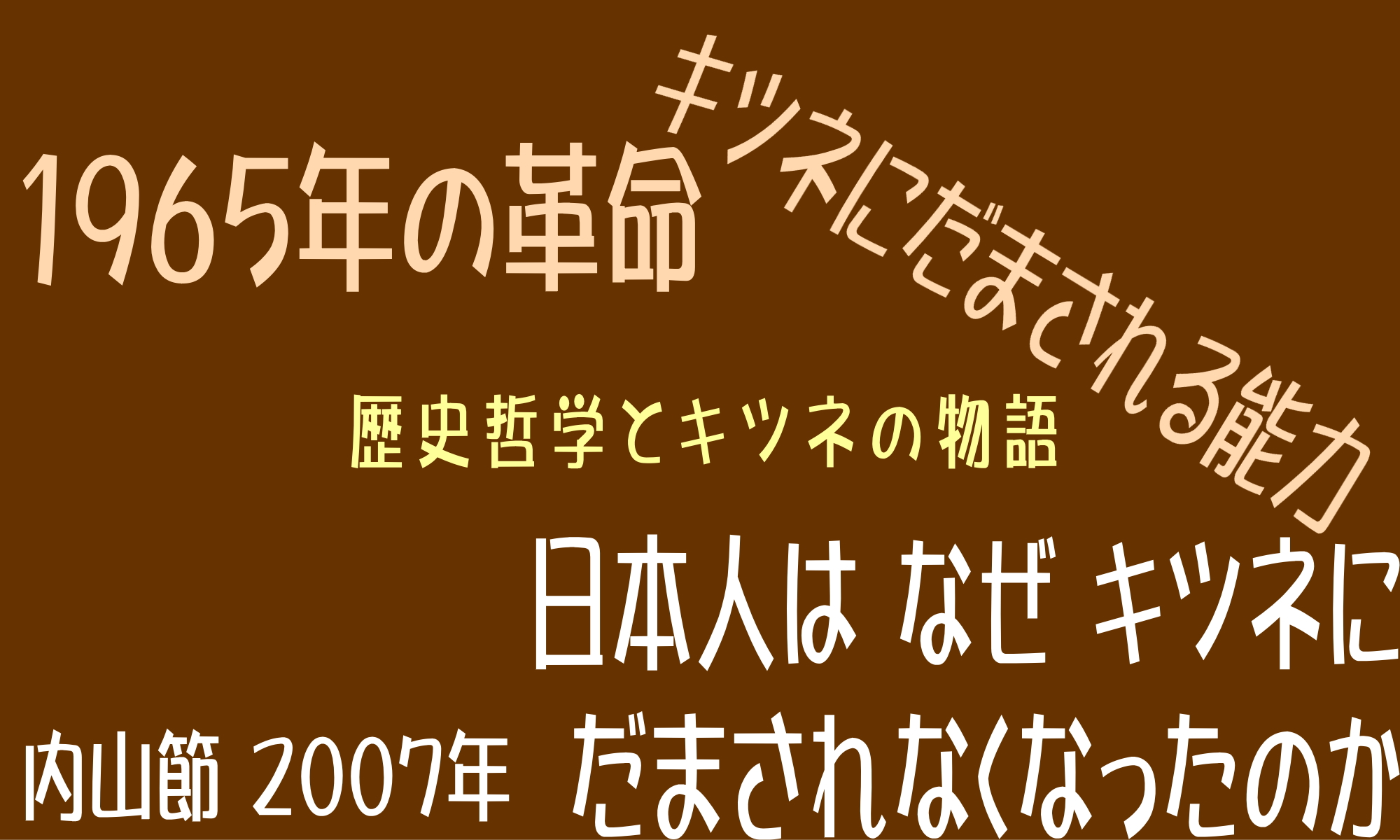百姓の、自立

田中圭一『日本の江戸時代 舞台に上がった百姓たち』刀水書房 1999年
p255 小見出し //わたしの江戸時代観//
//江戸時代には士農工商の秩序があって、武士には切り捨て御免の権利があった。人々は自給自足の生活を強いられ、食い扶持を残して余剰の多くは年貢にとられた。庶民は読み書きもできず、ひとたび病に倒れるようなことにでもなれば、神仏に頼む以外なすすべもなく死んでいった。江戸幕府の封建政治のもとで、人々は人間としての権利を奪われていた。
わたしたちは江戸時代をあらましこのように教えられてきた。わたしは、村の古文書や村のしきたりを自分の目でたしかめようと思い、半世紀近くのあいだ村を回った。私がみた村の実相は、それまで頭で描いてきた村の姿とはまったく異質のものだった。
佐渡小木半島宿根木村(おぎ・しゅくねぎ)の医者柴田収蔵は、天保・弘化のころの毎日の「日記」を残している。宿根木村は120軒ほどの村で、毎日数人の患者が彼の医院を訪れ、また、数軒の家に往診に出かけている。医療の水準は今日のそれとはちがうだろうが、町や大きな村には医者がけっこういた。しかも柴田の場合をみると、村人の医者に支払う金は薬代だけ、往診料は、漁師であったら魚がとれたときつけ届けをする、というようなものであった。医者が蓄財をするこんにちとは大きな違いがある。
村の子供たちは、柴田をはじめ廻船持ちや主(あるじ)や村の称光寺の住職の許に夜学して文字を学び、村の半数以上の人たちが文字が読めた。村人のなかで書物の貸し借りがさかんにおこなわれ、柴田は頼まれて書物の筆写に余念がなかった。無学文盲どころか、こんにちでは柴田が記した日記の文字を、わたしたちが読めないでいる始末である。//
※→ 識字率(識字力)
p256
//村の秩序は、江戸時代以前にあった身分関係に代わって、経済関係が重きをなすようになっていた。わたしたちは、地主と小作人の関係というと貴族とその家にいる奴隷のような関係であるかのように考えていたが、収穫の分け前は半分ずつで、家計・住居は独立し、小作人はみずからの計算と意志で小作をやめることができた。小作のなり手が多ければ、小作人は頭を低くして地主に小作を懇願したが、小作を希望する者がなければ地主が頭を下げた。小作人が他業で資産をたくわえれば村重立になり、名主をつとめる者もあらわれた。小作人は地主よりは貧しかったが、無権利で売買の対象になる奴隷や、中世の下人とはちがう。収穫物の二分の一を受けとるという確実な権利と、自分の意志で働き、移動する権利をもっているのである。また、士農工商という秩序はたしかに存在した。しかし、18世紀のなかば、佐渡矢馳村(やばせ)では、となり町の商人地主を招いて村名主になってもらっているし、越後塩沢村の商人大塚家は、高田藩の勘定役吉田伴蔵という武士を養子にしている。田畑が、「おおやけの検地帳」と「実際上の刈高帳」によって、形式と実際が円滑に動いていったように、士農工商という身分的な秩序は形式として残り、世の中の実際は、経済的秩序によって運営されたのである。
江戸時代のはじめに存在した身分的秩序と、世の中の変化の過程で生まれた経済的秩序を、人々はみごとに使い分けてきた。だから世の中の実質がどのように変わっても、形式との衝突が起きるということは滅多になかった。形式の主催者である藩主と、そこに住む住民たちの間に衝突が起きたときは、幕府・将軍がことの正邪を判断した。幕府と藩の間で避けがたい衝突が起きたときは、天皇がその間をとりなした。そこにわが国の天皇制問題の位置があり、おおやけの意味がある。
これまでわたしたちが江戸時代を形式の側からのみ みてきたことは明らかである。村人の生活をみるときは、「慶安御触書」を示して、人間として生きることを否定された民衆をそこにみた。検地は土地所有権の確認を求めて百姓の側から起きた要請によって開始され、検地帳は所有を確認する台帳であるのに、わたしたちは、この帳面によって農民が土地に束縛されたと論じてきた。どうしてそのような曲解がおこなわれたのか。それは江戸時代を世界的にも例をみない強固な近世封建社会の時代としてとらえようとする大前提があったからである。
げんに村で起きつつあるできごとは、封建社会の崩壊を告げるできごとばかりである。村でつくられる生産物はすべて商品として生産された。酒造屋の酒も女たちの織り出す縮も、山から伐り出す木櫨(ころ)も、みんな売るためのものである。百姓が自給生産物の余りをほそぼそと売って生きたとか、貧しさからのがれるために副業や出稼ぎに従ったとかいっていたら、こんにちの日本人の大部分は、農家が貧しいから会社勤めにでた、というような理屈がまかりとおることになってしまう。
江戸時代を封建社会の時代とみることには賛成できない。江戸時代わが国では重商主義が育ち、貨幣はすてに資本として動きはじめていた。あたらしい資本の時代への用意は万端ととのっていた。そうした実態があるにもかかわらず、江戸時代の民衆を無権利の土民に仕立てあげた一面の責任は、戦後の歴史学にあると思う。
形式の場面、つまりつぎつぎと出される法や制度を幕府の政策としてかかげ、民衆はいつもその被害者であることが強調された。さらに明治になれば明治独裁政府の横暴が、そして昭和になれば軍国主義者の横暴がとつづく。被害者の立場におかれるということは、心地良いことである。「秩序」とか「規則」とかいうものは、「自由」の前に消滅すべきものだと考えられた。江戸時代の村を語るときに、しばしば「村落共同体」という用語が用いられ、村落内の規制を身分的秩序のあらわれとしてとらえる。しかし、村人が自ら掟をつくるということを、ただちに封建制のせいだなどと考えてはならないと思う。村人が寄り合いをして村掟をつくるということは、村が独立している証拠である。入会山野の利用、秣(まぐさ)場の利用、用水・排水の利用規則、それらの維持のための協力、そのような問題を個人の勝手気ままにしておいたら、社会は自滅の淵に立たされることはいつの時代も明らかである。個々の百姓の独立が百姓の利害調整を必要とし、新しい共同体がつくり出された。それが江戸時代の村であり、村極(法律)は村の秩序である。百姓のつくりあげた村極と幕府の押しつけた禁令を混同してはならない。
明治のはじめ世界に鉄道が走る時代、わが国では駕籠かきが籠をかついで東海道を走っていた。この一事をもってしても彼我の差はいかにも大きく、決定的にみえた。しかしよくよく考えてみれば、それは動力機関の差に過ぎない。明治の識者がいったように、それは蒸気機関を買い入れてくれば済むことである。
しかし江戸時代以降の歴史を、被害者の歴史とみることは容易ならざることである。日本人はこの心地良い用語に酔い、その結果自らの責任を回避し、自立の歴史を語ることをやめた。世界でもっとも遅れて近代国家の一員になったという劣等感と、一世紀という短期間に世界の一等国になったという優越感が現代のわたしたちの精神にをおおっている。そして戦後は古い秩序はいつも打ち破るべきだと考え、我意だけを主張する社会がおとずれた。
日本の江戸時代を、村の側からもう一度みなおす必要があるとわたしは思う。百姓が自らどのような掟をつくり、何を権力に対して求めたか、こんにち幕府や藩の政策といわれているものの多くが、村人の要請によって生まれたこと明らかにする必要がある。村人の良識と、その良識によって選択した生活上の諸権利と緒規則が、江戸時代の社会そのものなのである。村人はイデオロギーのために生きていたのではない。//
田中圭一 たなか・けいいち
1931年 新潟県佐渡郡金井町に生まれる
1953年 新潟大学人文学部経済学科卒業、両津高等学校教諭、のち佐渡高等学校に転じる
1967年 京都大学国内留学
1976年 新潟県史編集主任
1987年 『佐渡金銀山の史的研究』(刀水書房)により第9回角川賞(国史部門)受賞、文学博士
1988年 筑波大学教授(歴史人類学系)
1993年 『帳箱の中の江戸時代史』により年新潟日報文化賞受賞
1994年 筑波大学退官、群馬県立女子大学教授
1996年 群馬県立女子大学退官、現在にいたる
※本書による著者紹介
田中圭一『百姓の江戸時代』ちくま学芸文庫 2022年 (ちくま新書 2000年)
p100
//昨今、慶安御触書については何人かの方々が見解を述べておられるので、ここでは立ち入ることを控えるが、げんに村に出されたどうかも怪しいものを、編纂された法典にあるというだけの理由で教科書に載せるというようなこんにちの「近世史」のありようは、問いなおされる必要がある。
江戸時代の法と制度からは幕府の悲鳴が聞こえてくるはずなのに、わが国の歴史学はヨーロッパ史学を丸呑みしてしまった。法の精神のかわりに封建的な政策意図を付けてみせたのである。世の中の実状を述べることなく、支配者の教条的な正論だけを並べたてた幕府体制論には無理がある。こんにちわたしたちが、ともすると道徳と法を分離できないでいるのは、この支配者史観にとらわれているからではあるまいか。//
※//このような法令としては、1649(慶安2)年に幕府が出したとされる「慶安の触書(ふれがき)」が有名であるが、その存在には疑問も出されている。」// 『詳説日本史』山川出版社 2023年 p170
※//「田畑勝手作りの禁」。こうした政策が存在したかどうか、近年、見直しされている。// 『詳説日本史』p170
p137 小見出し //本当の秩序は生活者の必要から生まれる//
//わたしたちは、秩序はあるよりないほうがよい、と考えている。しかし、そういったとりあげ方自体がすでに歴史的ではない。秩序は、あるほうがよいか、ないほうがよいかという角度からみるべきものではない。村や地域でつくられた秩序、たとえばノリやワカメの口明けの秩序は、資源を保護するために存在するのだ。そして口明けは資源利用の平等、利益の均等という問題とかかわっている。秩序は本来、必要によって生まれるものなのである。
佐渡海府地域の村では、第二次大戦後に至るまでシナ(科)の木の皮の口明けの制があった。口明けの日、個人個人が山に入ってシナの木の若枝を刈りとるが、その若木は村に帰ってそれを集め、ほぼ同量に分割してクジ引きで順位を決め、自分で選んでそれらをもち帰ることになっていた。良いものだけを収穫して資源が無駄になることを防ぎ、同時に分配の平等を実現するためであった。ある漁村では、とってきたアワビの目方(重量)をはかって、一定重量に達しないものはすべて海に戻した。
このようにみてくると、村人がとりきめた秩序(拘束)は、封建的秩序でもなければ身分的秩序でもなく、生きていくために必要な秩序で、それが生産の上で大切な役割を果たすかぎり、現代でも必要なものであることが納得できる。
江戸時代になって、中世には存在しなかったこうしたこまごまとした秩序が生まれたのは、それぞれ利害を異にする数十戸の単婚家族の家をまとめて村が成立したからである。秩序によって、山の生産物や海の生産物が最大限有効に利用でき、平等に分けられ、しかも資源が枯渇しなかったのである。
このような秩序が存在しなかったら、こんにちわたしたちが利用する資源は絶滅していただろう。戦後、民主主義の風潮によって、このような秩序は排除すべきものとされた。そのために根絶やしになった資源も決して少なくない。そう考えてみれば、歴史学こそ人の生きる環境を守るために、こうした社会の循環や秩序についてもっとも大きな役割を果たすことが期待される学問分野である。
しかしいまのところ、わが国の「近世史」が、江戸時代からの情報として、そのような問題について意見を述べたのを聞いたことがない。秩序を、領主権による生活統制と考え、秩序の排除を近代化と考えているかぎり、過去に存在した秩序から学ぶことはできない。
村人のつくった秩序は、個々の家が独立して存在していくために条件であった。だから、村の秩序は当否を論ずるまでもなく、いらなくなれば自然に消えていくものなのである。支配の脇役である幕府が自分たちの都合でつくった秩序など、主役である村人に守られたためしはない。秩序というものを、いつも支配者が被支配者に押しつけるものだと考えていることが、すなわち支配者史観なのである。//
p154
//江戸時代初期の市場の構造は、農民を商品販売者とさせず、領主の販売する商品を中心とする幕藩制的な市場構造をつくったことに特徴があった。
こういう論説が通説として流布されているが、もう時代は大量の商品を必要としていたのであって、一大名が百姓から何を集めどこへ売ろうとするかによって流通市場が動く時代ではなくなっていた。江戸時代初頭の商業を、領主的商品の流通時代だ、とする「近世史」の通説は再検討される必要がある。
わたしはこれまでも機会あるごとにこのことを主張してきたが、それにもかかわらずほとんどすべての教科書が、自給自足社会論をいまもかたく守っている。それは基本的に、江戸時代は武士が経済運営の主役であるということを主張するためである。そうでないと、武士は歴史の主役の座にとどまれず、「近世」という封建国家像が崩れてしまうからである。江戸時代が封建社会であることを認知させるための「近世史」のありかたは、決して好ましいものではない。//
p160
//簡単に言ってのければ、江戸時代の農民は自給していても、家族はそれぞれもうけになる仕事を選んでいるのである。そういう意味ではみんな二足のわらじをはいていた。そのような村人を百姓とよぶのである。//

百姓の、自治
柿﨑明二『「江戸の選挙」から民主主義を考える』岩波書店 2023年
p71 小見出し //投票した百姓の識字率94%//
//国民の知的水準の基準とされ、民主主義発展の条件ともされる識字率は、江戸時代後期で、男女、地域で差はあるものの40%程度と見られている。これは他国と比べても遜色ないものだった。特に村役人に限れば、年貢の割り振り、文書の読解、作成が重要な業務であり、ほとんどが読み書きや計算ができたと考えられる。読み書き、計算が不得意であるために名主就任を辞退、あるいは高齢で読み書きができなくなったことを理由に退職するケースもあった。
民衆の教育にも詳しい歴史学者の高橋敏氏は1856、57(安政3、4)年に行われた駿河国駿東郡御宿村(静岡県裾野市御宿)の村役人の入札についての研究で、投票した百姓の識字率が94%前後だったとした上で「19世紀後半の村落社会において、戸主層にあってはそのほとんどが識字力を身につけていたとみてよいでしょう」と述べている。//
p72 小見出し //江戸は未開でなければならなかった//
//江戸時代から明治時代への歴史を、一般的な教科書で学んでくると、ある錯覚に陥る。時代区分が変わると、途端に人々の生活も激変したかのような印象を抱かされるのだ。明治維新を迎えると、人々はちょんまげから散切り頭になり、洋装が散見されるようになり、極端な場合は明治になった途端に機関車が走る、といったイメージである。
「ザンギリ頭をたたいてみれば文明開化の音がする」という、当時のはやり歌(都々逸)の訴求力が強すぎるためか、明治になったら社会が欧米風に一変したという印象が植え付けられている。さらに、映画やドラマといった映像の娯楽においては、時間の制約から数年、数十年単位で場面が飛ばざるを得ないことも手伝って、鮮やかな変化が強調される。
しかし、当時の人々からすれば時代の変化は徐々に少しずつ進んでいくものだろう。戦争や大災害でもなければ、今日はだいたい昨日と同じで、明日も今日とほぼ同じである。それが、いろいろなことがきっかけで振り返ってみて大きな変化に気づき「世の中変わったんだなあ」と感慨にふける。これは現代でも変わらない人々の時代認識であろう。
逆に言えば、同じように見えても、日々気が付かないような変化は、さまざまな分野、領域で少しずつ起きている。その変化がある閾値を超えると、人々からいっせいに「時代は変わった」と認識されるのだ。この閾値を超えた時点にのみ焦点を当てると、日々起きていた小さな変化を見落とすことになる。
明治新政府が日本の舵取りをし始めた当初、自分たちの体制は未成熟で、大名など旧勢力も残っており、さまざまな軋轢に苦しんでいた。庶民の間にも江戸時代を懐かしむ空気があった。新政府の命令で大名が地元を離れるのを引き留めようとする一揆まで起こった。
ミスがあれば体制が転覆しかねない状況で、新政府は、江戸時代を辛く暗い封建制の中に閉じ込めなければいけなかった。現代の政権交代時にも使われる印象操作だ。江戸の村に高度な自治と民主的傾向が進化していた事実は、なかったことにしなければならなかったのだ。
自分たちが政権を握ったことで、未開で悲惨な江戸の治世から国民を解き放ち、文明を開化させた、というのが新政府の存在意義だった。これと、わかりやすく時代区分をしなければならない歴史教育は親和性が高い。さらにそういった教育を受けた一般の人々の認識に依らざるを得ないエンターテインメントが加わり、イメージは固定される。
粗末な衣服を着けた百姓家族が囲炉裏にかけた鍋から雑穀や野菜を煮込んだ汁を食べている。寒空の下、鍬を肩にかついで、荒れた田畑を茫然と見つめる百姓。年貢を納められなくなった百姓が名主や代官に土下座して延納を懇願する。追い込まれた百姓が自暴自棄になって竹槍をかざして一揆を起こす──。とても貧しく、何も考えられず、哀れな村々の百姓というイメージの完成である。
確かに飢饉など、イメージ通りの悲惨な実態はあり、場合によってはもっと過酷なこともあった。しかし、数百年もの間、同じような状態が続いたわけではない。今、不幸なのは、そんな境遇にありながらも、よりよく生きようと試行錯誤を続けた百姓の努力とその到達点が忘れ去られることだろう。そうなれば、私たちは祖先の暮らしから今日的な教訓をくみとることができなくなってしまう。江戸時代の村の民主的傾向を、民主主義の観点から捉え直す意義はそこにあると思う。//
柿﨑明二 かきざき・めいじ
1961年生まれ
早稲田大学 第一文学部卒業
毎日新聞社を経て共同通信社に入社。政治部で首相官邸、旧厚生省、自民党、民主党、社民党などを担当。政治部次長、論説委員兼編集委員。菅義偉内閣首相補佐官などを経て2022年より帝京大学法学部教授。
※本書による著者紹介

百姓あっての幕藩領主
山﨑善弘『徳川社会の底力』柏書房 2017年
p29
//ここまで見てくると、徳川時代の「強固な国家、みじめな民衆」という通念が誤りであることは、もはや疑いようがありません。//
p34
//すなわち、撫民は幕府によって打ち出されただけで、幕藩政治の普遍的理念として定着したのではなく、年貢減免などへ向けた百姓側の抵抗もあり、それらが促されながら、理念としても実体としても幕藩領主に共有されるに至るのです。したがって、仁政が幕藩政治の中に定着し出すのは17世紀後半でした。//
p45
//平和が続き、社会秩序が安定する中で、全領主階級に軍役を課し、そのことによって将軍の絶対性を示すような権力編成の方式は、もはや時代にそぐわないものとなっていたのです。綱吉は、武力による支配よりも仁政を行うことを重視し、軍事から政事への転換を確たるものとしたのでした。//
※徳川綱吉の政権前半期(1680~1683)「天和の治」
p116
//ところで、浅間山の噴火〔1783年〕後の民間の動向として、被災した村々に対する近隣の人々による援助についても見ておきたいと思います。壊滅的な被家を受けた鎌原村では、小高い観音堂に逃れていた老人・女・子供93人が助かりましたが、泥流に埋まった村で途方に暮れていました。この状況を見かねた近隣の吾妻郡大笹(おおざさ)村の名主長左衛門(ちょうざえもん)、干俣(ほしまた)村の名主小兵衛(こへえ)、大戸村の安左衛門(やすざえもん)の三人は、各々の家に93人を引き取り、食事などを与えて介抱しています。噴火が収まってからは、村の跡地に小屋掛2棟を造って住まわせ、麦・粟(あわ)・稗(ひえ)などを少しずつ送りました。そして、「93人は真の一族と思うべし」と諭して、親族の契約をさせ、夫を失った女には妻を失った男を取り合わせ、子を失った者には親を失った子を養わせ、新しい家族を作らせたのです。当時の村落生活のあり方からすれば、家族や一族を基礎としてしか村の再建はあり得なかったのです。そうして被災を免れた耕地は、新たな一族へ均等に配分されました。
右の三人は、鎌原村以外の被災した村々も救済しており、こうした奇特な行いを認められて、幕府からその身一代の帯刀と、子孫まで苗字を名乗ることが許され、銀10枚も与えられました。幕府としても、民間の救済力は歓迎されるものだったのでしょう。民間の救済力にも支えられて、村々の再建は進んだのです。//
2024.1.14記す