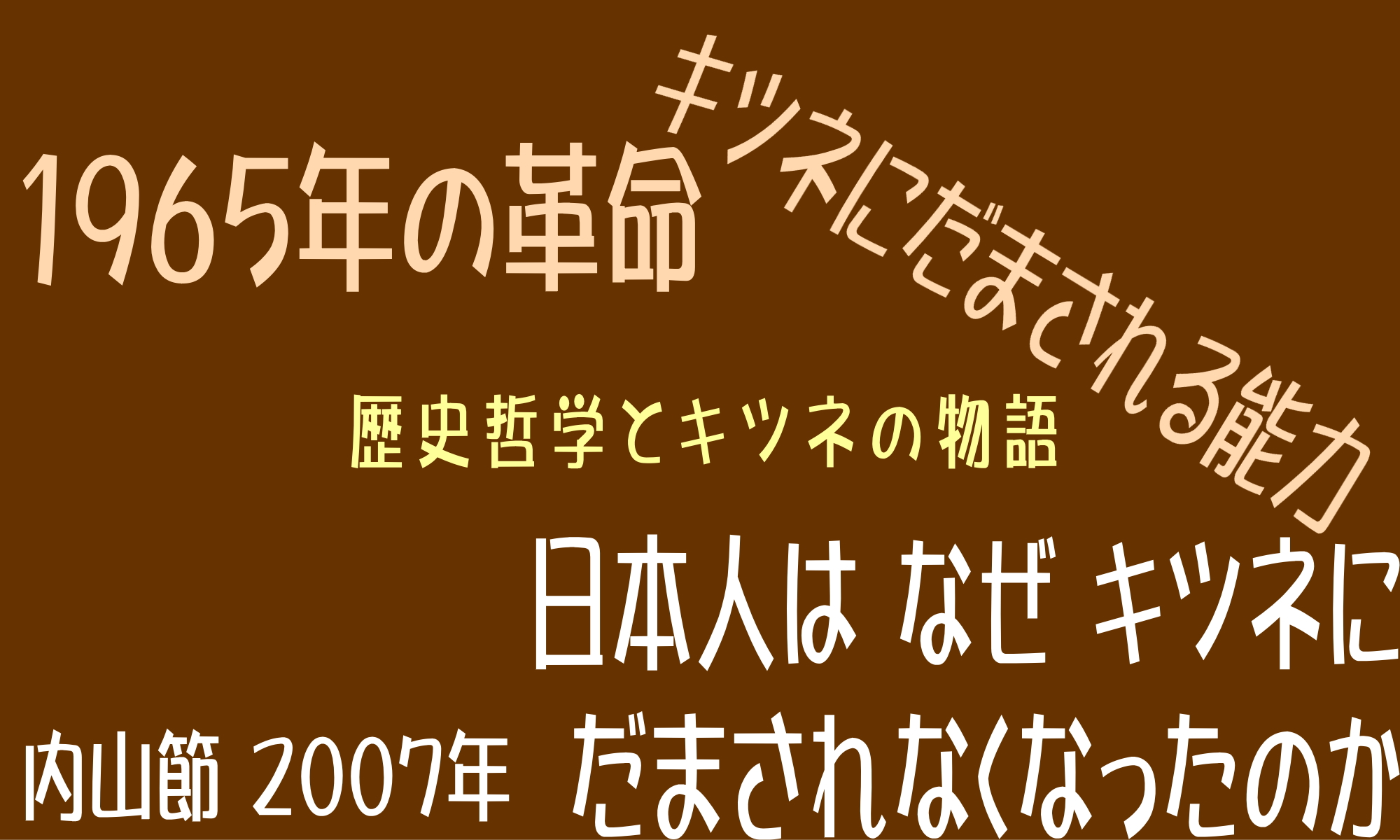幼児は競争しない
運動会で勝つと喜ぶ。負けると悔しがる。勝負だから、勝ちたいと思う。でも、走っている様子に懸命さはあっても、それでは勝てないなあと応援席では思ってしまう。負けたら残念がるが、あっけらかんとしている。勝負は、努力なしで自然にころがりこんでくるものではない。わたしはかねてより、幼児は競争しないなあと思っていた。──しかし、その理由を説明できないままでいた。
藤田晢也『心を生んだ脳の38億年』岩波書店 p45
//自己と自己の子孫の生存に向けた、自発性と合目的性の原理が確立され、生きものはその原理の上にのみ、進化のふるいをくぐりぬけて存在するようになっていったのです。
このようにして、安定した自己存在を保証された細胞という境界のある体制は、同時に他者と異なる主体性というものを、個々の生きもの〈細胞〉に与えることを可能にしました。「自己存在」の発生ルーツがここにある、と考えられます。//
上記は少々むずかしいかもしれない。あらゆる地球上の生物は、生き残るために目的をもっているということである。脳機能が「目的」をもつことで、安定した自己存在すなわち主体性が生じる。
学齢に達すれば、競争を意識することで学習意欲が高まることも期待できるだろう。しかしながら、幼児期(乳児も含めて)は脳機能の発達において、生得的にもっている脳の目的性によって前進してゆく。
リレーで勝ち負けのある勝負にのぞむが、競争というルールを身につけるものの、5歳児の競技は競争ではなく、合目的性の延長上にあるといえるだろう。
2026.1.15記す