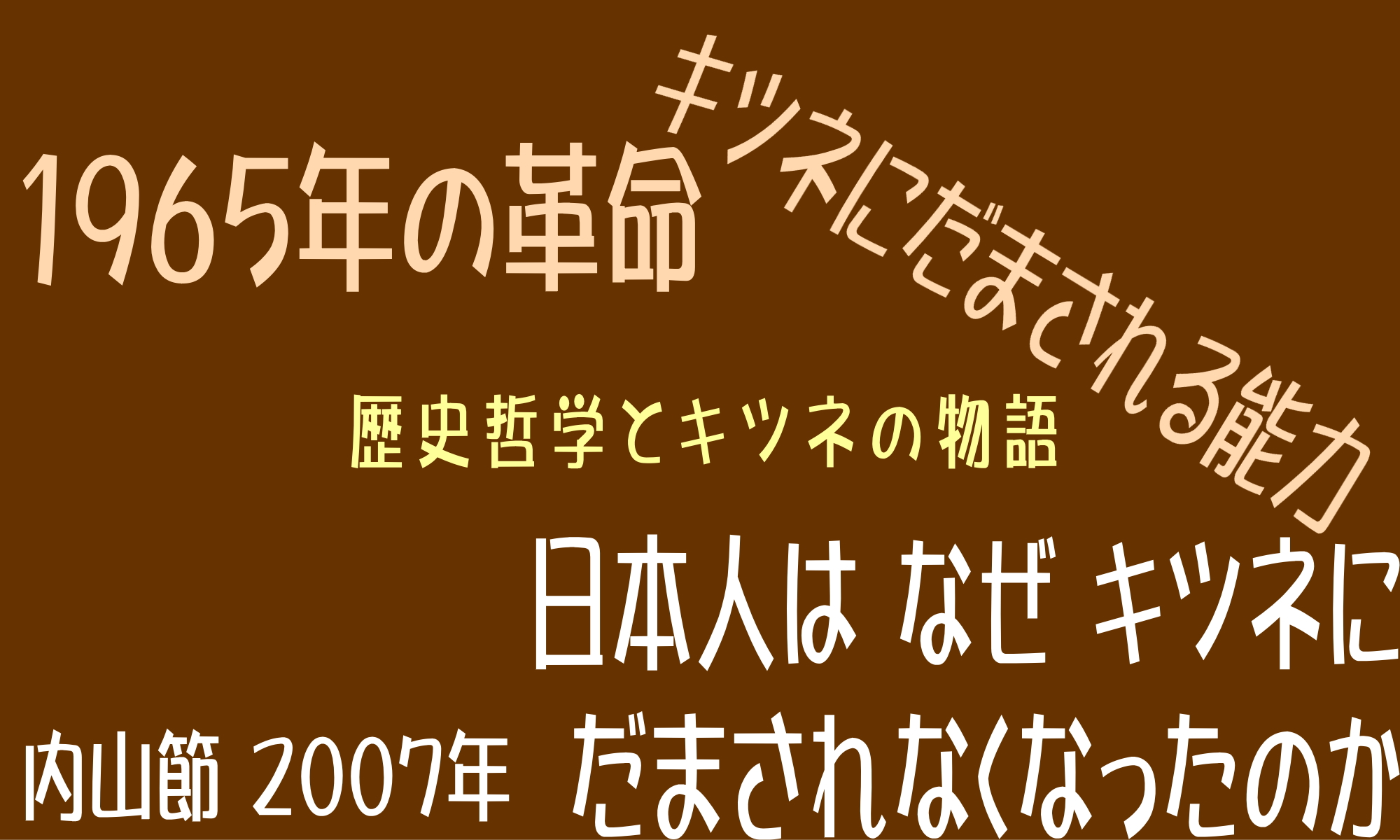Home > 4+ カルテット・プラス > 脳神経:トップ > 意識
Home > 4+ カルテット・プラス > 脳神経:トップ > 意識
脳のなかでこそ、ケシの花は赤く、林檎は香ばしく、ひばりは歌う
オスカー・ワイルド
『意識をめぐる冒険』p2 ※後段↓参照
+ マルチェッロ・マッスィミーニ
+ ジュリオ・トノーニ
『意識はいつ生まれるのか 脳の謎に挑む統合情報理論』
+ 訳:花本知子
+ 亜紀書房 2015年
p19
//「意識」という用語の使われ方が、途方に暮れるほど千差万別で、定義もさまざまであることに気づくのだ。「意識」という言葉は、ある場面では「道徳的な自覚」を指して使われ、別の場面では「自意識」という意味で使われる。またある場面では、「外部からの刺激に反応できる状態」を指す。「意識」という言葉の語義だけを見てもこのあのさまだ。//
p20
//イギリスの学者スチュアート・サザーランド〔1927年生まれ〕は自著『心理学事典』の序文で、いらだちをこのように表現している。
意識というのは魅力的な現象ではあるが、とらえどころがない。それがなんなのかを定義することは不可能で、どのような働きをするのか、なぜ発達したのかもわからない。このテーマについて読むに値するものはまだなにも書かれていない。//
理論から入らず、直感や感覚を優先させて説き始める。舞台は、解剖室。
p23
//そう、次は自分の番だと想像してみてほしい。//……//この湿ったゼリー状の物質が、あなたの宇宙と同じくらい広大な宇宙を宿していたのだ、と感慨にふけることもできる。それがいま、あなたの手のひらに重みを伝えながら載っているのだ。あなたのすべてが、知識、記憶、想像、夢のすべてがつまっているのは、そのへんにころがっている物体と同じようにとったり渡したりできる”モノ”なのだ。大脳は輪郭と重さを持つ物質である。//
※宇宙……ここが表記されているページを遡ると、宇宙飛行士の話がある。月に立った宇宙飛行士は自身の指一本で地球が隠れてしまった。地上にいると”地球”のことがわからない。意識についてもわからない。脳もわからない。ここを出発点にしよう、ということだ。
「要素のあつまり(分けられる)」と「一なるもの(分けられない)」
p266
//これまでに、客観的な基準〔意識レベルΦ〕でもって、ある物体が「一なる組織」であるか、それとも「小さな要素の集合」であるかを定めた者はいない。われわれは直感的に、まわりのモノとはっきり区別される輪郭を持つ物体を、一なるもの、と見なしてきた。//……//だが客観的に見て、こういったものに〔※〕一なる性質があるとはいえない。見た目にそう映るだけだ。実際、われわれは外見から判断して、いつもだまされている。だが一なる性質、いいかえれば統合性は、当の物体の内側にあるものから判断しなければならない。//
※//惑星や山、デジタルカメラ、細胞など、数え切れないものを、一なる物体だと思ってきた。//
p267♥↓
//物体が一なる組織か否かの基準になるのは、その組織を構成する要素間に因果関係があるかどうかである。そして、要素同士に密接なつながりがあり、それによって、情報を組織全体として生みだしているかどうかがポイントになる。独立した要素が生むばらばらの情報ではなく、まとまった情報があるかどうかが目印となるのだ。//
「暗い」と気づくには
p156
//理論から実践に移るため、ここでしばらく、暗い実験室に戻ってみよう。//
p266
//光か闇かを見分ける架空の実験で、明確な例証が得られた。記憶に残る例である。デジカメは、外側からはひとつのものに見えていたのに、じつはまったくそうでなかった。各フォトダイオード間には因果関係がないため、デジカメのセンサーは一なる組織ではなかった。それゆえ、センサー内には統合された視点が存在しなかったのだ。その証拠に、センサーを細かく切り分けても、デジカメの機能は少しも変わらなかった。//♥↑
差異と統合が同時に成り立つ
p118 情報量:第一の公理
//意識の経験は、豊富な情報量に支えられている。つまり、ある意識の経験というのは、無数の他の可能性を、独特の方法で排除したうえで、成り立っている。いいかえれば、意識は、無数の可能性のレパートリーに支えられている、ということだ。//
p125 統合:第二の公理
//意識の経験は、統合されたものである。意識のどの状態も、単一のものとして感じられる、ということだ。ゆえに、意識の基盤も、統合された単一のものでなければならない。//
p126
//ここで、第一の公理と第二の公理を組み合わせると、理論のかなめとなる命題が得られる。//
※以下↓
p126
//意識を生みだす基盤は、おびただしい数の異なる状態〔差異〕を区別できる、統合された存在である。つまり、ある身体システムが情報を統合できるなら、そのシステムには意識がある。//
※素人ながら わたしがここで思うことは「顔認識」。あるいは、乳児が母を認識(意識)すること。
※主体論に結びつける試み……いわゆる”自意識”を排除した上で、「差異と統合」理論は、個としての主体を捉えるに適切ではないかと考える。他者が個を見る場面、個が自身の個に向かう場面(自意識とは違う意味)、それぞれの主体を「一なるもの」として捉えるために。
※宇宙論に結びつけると……ビッグバンから悠久の時が経ち、カオスの中で「差異と統合」によって「一なるもの」が生成される。稀ではあっても。とすれば、そこに”主体”が生まれる。
動物に意識がある・ない──意見が分かれる理由
p237
//動物に意識があるのか否かについて、これほどまでに意見が分かれるのには、明確な理由がある。世界に存在するものに意識があるかどうかを見分けるためには、確かな原則と、できれば測定も必要だ。だがいまのところはない。そういったものが見つかるまでは、類推に基づいて考えざるを得ないのだ。あるいは、もっとひどい場合、たんなる個人的な好みに基づくだけだ。//
意識と無意識のあいだ
p257
//意識と無意識のあいだに、はっきりした境界があるとは考えにくい。//
※空や宇宙の”はて”もそうだなあ~。「あいだ」という空間設定が間違いでないか。
クリストル・コッホ『意識をめぐる冒険』岩波書店 2014年
p13
//本書では最後に、ある種の高度に組織化された物質、特に脳に、どうして意識が宿るのか、その理由を説明する可能性がある、非常に有望な意識の定量的な理論について述べる。「統合情報理論」と呼ばれるその理論は、神経科学者で精神科医でもあるジュリオ・トノーニが考案したものだ。統合情報理論は、二つの基本的な原理からスタートし、どのようなシステムに、どのような意識が生じてくるのかの説明を試みる。統合情報理論は、頭のなかだけで推測を重ねるような哲学理論ではなく、具体的に意識がどうして脳から生じるかについての神経生物科学的な理解につながる。さらに将来的には、動物や乳児、睡眠中の被験者や脳に障害を受けた患者など、自らの意識経験を語ることのできない生き物において、どの程度の意識があるかを測る「意識メーター」の開発につながることが期待される。統合情報理論には、イエズス会の古生物学者であり神秘哲学者でもあったピエール・テイヤール・ド・シャルダン(1881~1955)の考えと似た部分がある。//
p256
//歩みを止めることのない探求の途上でフランシスと私は、情報の二面性と意識の関係性をうまく説明する、ジュリオ・トノーニの理論に出会った。//……//ジュリオの理論の中心になっているのは、「統合された情報」という概念〔統合情報理論〕だ。//……//若手であるジュリオと私は意気投合し、時間が経つにつれて仲間意識は強まるばかりだった。//
※フランシス……フランシス・クリック 1916-2004。//1953年にジェームス・ワトソンとともに、遺伝子の本体であるDNAの二重らせん構造を発見した。この20世紀最大の革命的な発見によって、1962年に二人はノーベル賞を受賞//(p10)
p43
//見たり、聞いたり、触ったりするもの〔即ち、五感〕が意識にのぼったり、何かについて考えたり〔思考〕、思い出したりする〔記憶〕のはすべて意識の働きによる。//
p44
//物理現象〔ニューロンが伝播する電気信号など〕から主観的な意識世界が生まれる仕組みは謎に包まれていて、まるで魔法のようだ。//
p45
//深い睡眠に落ちたり、昏睡状態に陥ったりしないかぎり、私たちには常に意識があるし、意識的に何らかの感覚を感じている。//……//意識があるということは、生きていることの証にほかならない。//
p45 主観
//私たち一人ひとりが世界を感じる見方、意識の内容は「一人称の見解(主観)」と呼ばれる。この「主観」というものが、どのようにして単なる物質に宿るのか、それはこれまでの科学ではまったく手がつけられなかった問題だ。//
p45
//確かに、脳は高度に秩序だった物質であるが、どうしてその脳の内部だけからしか経験することができないような視点が生じるのか? 他人の主観を私たちが経験できないのはなぜなのか? 他の多くの領域では、さまざまな事実を明らかにしてきた科学という方法が今のところ、この問題に関してはなすすべがない。//

p54 クオリア
//何かを経験するということは、ある特定のクオリアを感じることだ。そして、ある特定の経験のクオリアは、他の経験のクオリアとは異なる。
クオリアは自然界に備わる基本特性であると私は考えている。クオリアは、天から降ってきたものでも超自然的なものでもない。どのような自然法則に従ってクオリアが生じているのかを明らかにするのが、私の最大の研究目標だ。//
p62
//脳は、数億回の世代交代を経て進化してきた自然選択の産物だ。生存に有利に働く機能がクオリアに何も備わっていなかったならば、ここまでクオリアが残っていることなどありえないだろう。//
p63 意識の定義は難しい
//私が以前、動物の意識を紹介する講演を終えたところで、一人の女性が大声で叫びながら近づいてきたことがある。「コッホ博士、私はサルに意識があるとはどうしても思えません!」 そこで私はすかさず言い返した。「あなたに意識があることも私にはわかりませんよ」。女性は私の返答に驚いていたが、その顔にはすぐに理解の色がみられた。//
※理解の色……これもクオリアだな。
p65
//よくある誤解の一つに、「科学はまず研究対象となる現象を厳密に定義し、その後にその現象を支配する原理を明らかにしてゆくものだ」という見方がある。ところが、歴史的にみれば、科学はそうした正確で明瞭な定義なしに進んできた。科学者たちが使う定義は、知識の蓄積に併せてフレキシブルに変わっていく、融通の利くものだ。そうした「作業定義」が議論や実験のきっかけとなり、異なる研究分野間での交流が促され、科学は発展してきたのだ。//
p66~p68
//こういう態度を踏まえたうえで、私なりの4つの意識の定義を紹介しよう。//
(1) //私たちが日々経験する精神生活そのものである//……//旧約聖書の「伝道の書」はいい点を突いていた。「生きている者は自分がやがて死ぬことを知っているが、死んだ者は何も知らない」。//
(2) //外から見て判断できる動作や行動//
(3) //意識が成立するために必要最小限の生理学的な仕組み//
(4) //何かを感じるときの感じ//……//自分の内面でどんな感じがするか//
※(4)では「発達の最近接領域」を連想した。
p73 自意識
//意識の最も重要な側面は何かと訊ねると、自分の意識の中身を振り返る能力、つまり自意識を挙げる人が多い。//
p74
//ところが、われわれの日常によく起こる現象を考えてみれば、この結論はおかしいとすぐに気づくだろう。//
p76 //映画を観たくなる理由//
//映画は、日常の雑多な心配ごと・不安・恐怖・疑念といった自意識から引き離してくれる。上映されている数時間のあいだ、私たちは別世界の住人になれる。スクリーン上で展開されるストーリーに対する意識は高まるが、自分自身の内部状態にはほとんど気づかなくなる。そしてその経験はときに、このうえない喜びをもたらしてくれる。//
p77 言語のおかげで……
//自意識と並ぶ、人間固有の特性が言語能力だ。人間は言語を獲得したことで、概念を表現したり、記号を操作したりして、他人とコミュニケーションをとることができるようになった。言語のおかげで大聖堂が建ち、スローフード運動が展開され、一般相対性理論が考案され、詳説『巨匠とマルガリータ』が書かれた。どれもが、人間以外の動物にはできないことだ。文化生活は言語なしには成り立たない。そのため、哲学者や言語学者たちのあいだに、意識は言語なしには生まれず、ものごとを感じたり内省できたりするのは人間だけだという考え方が生じたのも無理はない。
しかし、私はそうした見方には賛成しかねる。言葉を口にできないから動物には意識がないとか、脳の発達が未熟だから赤ん坊に意識がないなどというのは、当人に意識があるかどうかの判定の根拠にはならない。そもそも、重度の失語症で言語能力がまったくないような人々にも意識はある。//
p78~p79 感情は必要でない
//感情は、意識とどういう関係があるだろうか? 生物体が意識をもつためには、怒りや恐怖、むかつきや驚き、悲しみや興奮、といった感情が果たして必要だろうか? そうした強い感情が我々の生存に不可欠であることは疑いないが、それが意識に不可欠であるという説得力のある証拠はない。自分が怒っていようと幸せだろうと、目の前にロウソクの火があれば、それが見えることには変わらないだろうし、その炎に手をかざせば熱く感じることにも変わりないはずだ。
それに、感情がない人にも意識があるという証拠は数多くある。//……//意識が成立するためには感情は必要ではない。//
2024.10.21記す